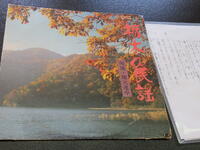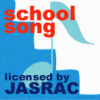校長瓦版
ストップ・ザ・止まってくれない栃木県

横断歩道で歩行者が待っていたら、止まらないのはマナー違反ではなく法律違反であるとの認識が必要なのでしょうか。道路交通法第38条第六節の二「横断歩行者等の保護のための通行方法」には、
①歩行者の有無を確認できなければ、横断歩道の停止位置で止まれるような速度で進行する。
②横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者や自転車がいるときは必ず一時停止をする。
③横断歩道内およびその手前30mは追い越しや追い抜きが禁止。
などが規定され、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、ドライバーは横断歩道の直前でクルマを一時停止させ、通行を妨げないよう義務付けています。横断歩道を渡るのに時間がかかってしまう高齢者や幼い子供も、もちろん例外ではありません。違反者には反則金や違反点数が科せられます。ポイントは
①横断歩道の手前で車両は一時停止して歩行者又は自転車の通行を妨げない。
②横断歩道又は自転車横断帯ありの路面標示により歩行者又は自転車を確認。
③歩行者や自転車の通行を妨げずに交通ルールとマナーを守る。
の3点でしょうか。
「意識が変われば行動が変わる」と、ある心理学者が言っていました。
昨日、栃木警察署で交通課の方が講話の中で「警察官はもう始めています。是非、教員も始めていただきたい。」と話していました。早速実践したいと思っています。
しかし、一時停止をしていたら、生徒が目の前で対向車にはねられてしまった教師の話を聞いたことがあります。私も止まっていたら、後ろの車に猛スピードで追い越されたことがあります。悲しいことですが、子ども達には「横断歩道で車が止まってくれても、周りの安全をよく確かめてから渡りなさい。」と教えなくてはならない現実があります。
法律を守る大切さは分かっていても、いざスピード違反や一時停止違反をしてしまったとき「何で自分ばっかり」「みんなやっている」といった言い訳をしてしまいがちです。法によって守られていることは気づかずに、自分が罰せられると邪魔に思ってしまう…。その言い訳は、校則を破った生徒の常套句であり、クレームを付けてくる大人の常套句です。
大人の悪いところは、子どもはしっかりまねをする、世の常です。小さい頃から、法律を守ることの大切さや、決まりを守ることの大切さを教えていかなければと思います。軽犯罪法や道路交通法を分かりやすく丁寧に教える必要があると感じています。
県警もCMを作って対策に乗り出しています。私たち大人達が本当の意味で道路交通法の意味を理解したときに、横断歩道も初めて安心して渡れるのだと思います。
7月8日は晴れた月曜日でした。


土日の2日間に収穫できなかったキュウリがこんなにたくさん…。


抱えきれないほどのキュウリを持って、1年生は教室へと…。
よく見ると、スイカも大きくなってきています。
 サマースクールの水泳のあとに藤井っ子のお楽しみです!
サマースクールの水泳のあとに藤井っ子のお楽しみです!

さて、階段途中の掲示板は、七夕に願いを込めて短冊が掲示してあります。一人一人の願いが叶うように、思わずほほえんだり、サポートしようと思ったり、一緒に願いが叶うように祈ったり…。
昨日は七夕でしたが今日は何でもない日です。何でもない日ですが、藤井小ではあいさつ週間が始まりました。「目を見てしっかり」や「心を込めて」といったプラカードを持った6年生が、学校の挨拶をリードしてくれています。




また、藤井っ子タイムでは、いつも6年生が司会進行を務め、給食保健委員会の発表も委員長の6年生がリードしています。最上級生として、グイグイ藤井小学校を引っ張ってくれている6年生に、拍手、拍手と思っているのは、私だけではないと思います。
「衰退感」と「衰退」
昨日、学校保健給食委員会の開催に当たり、東京から講師を招きました。校長室での懇談では、その先生から「卒業した小学校も中学校も廃校になっている」との話がありました。廃校になるのは、田舎の小学校ばかりではなく、都会にも同じことが起きていたことを忘れていました。生活する場、人とのつながり、「コミュニティ」が廃れていくと学校はなくなることを再認識しました。栃木県内では2000年以降100を超える小学校が廃校になりました。本校は複式学級のある4学級の小規模校です。全校児童は38名です。


全校運動(小規模校の特色ある活動)
学校がなくなると地域疲弊のシンボルになる可能性があり、「衰退感」が先行する。実際に生活が不便になっていくのが「衰退」で、なんとなく将来が先細りになる感覚がコミュニティに負の影響を及ぼしていくのが、まさしく「衰退感」である。こんな内容の記事が新聞に載っていたことがあります。全国から小規模校や地域の方が集まったシンポジウムでのことです。
「衰退感」を取り払うものは何か…。子ども達の生き生きとした姿であり、確かな学びを提供する学校であり、それを支える保護者であり、熱を持った大人のいる地域であると、この藤井小学校に来て感じました。
四者一体となった取り組み(私は4WDと言わせていただいています)が、「衰退感」を吹き飛ばす風を起こすと信じています。この藤井小学校を存続させるための、本気の取り組みが始まって数年だと聞いています。146年の伝統を誇るこの藤井小学校ですが、先輩諸氏の築き上げた輝かしい歴史と伝統は、必ずしも明るい未来を保証するものではありません。明るい未来を築くために、小規模校のメリットを最大限に生かすために、知恵と勇気と体を使って取り組んで生きたいと考えています。
道路交通法(運転者の遵守事項)第71条の1


しかし、いつもにこっと笑って挨拶をしてくれる児童が、うつむいたままでした。登校途中に車に水を掛けられ、ズボンがびしょ濡れになっていました。スクール・ガードの方々や職員からも「体育着に着替えようね」と声を掛けられたいましたが、うつむいたまま階段を上がっていきました。私も声は掛けてみたものの、一日のスタートが最悪になってしまった彼に更なる励ましの声をと思い、担任や養護教諭に事情を話しました。かつて「学校の先生に教わんなかった?」と言いながら悪を懲らしめるドラマがありましたが、「雨の日に車を運転するときは歩行者に水を掛けないように注意しなさい」と教える教師はいません。運転免許を取得するときの、教習所の教官の教えを守り、実践している人が多ければ…。
道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
違反すれば、刑事処分として5万円以下の罰金、行政処分としては普通車なら6千円の反則金、民事上は慰謝料の請求もできることになっています。しかし、実際は裁判にはならないし、立証も困難です。
学校で児童に「雨の日は、車と水たまりに気を付けなさい。水を掛けられても大丈夫なように、全身を覆う雨具か着替えを用意しなさい。」と指導しなければならないとしたら、少し悲しいです。
運転マナーではなく、守らなくてはならない法律である、そうした自覚が私も含めたドライバーに必要なのだと思います。大人にされたように、子どもはしますよね、きっと。人に優しい運転を心掛けなければと思います。
1年生の短作文発表


テーマは「自己紹介」でしたが、二人とも1年生とは思えないほどしっかりとした発表でした。「1年生になって、友達ができて本当に良かった。」「ひとのいやがることは止めましょう。」といった、自分の考えを堂々と、全校児童の前で大きな声で発表しました。
小学校に入ってまだ3か月。いつの間に、こんなに立派に成長したのだろうと感心しました。でも、これも藤井小学校の魅力です。上級生が、今までに何人も発表をしています。上級生は、本当に親切に下級生の面倒を見ています。上級生の「お手本力」が、この藤井小学校の大きな魅力の一つなのです。これからも1年生は、登校班やなかよし班での上級生、特に6年生の姿から多くのことを学んで成長していくと思います。6年生の「お手本力」と1年生の「伸びる力」にワクワクする毎日が、これからも続く藤井小学校です。